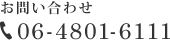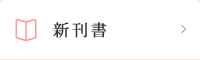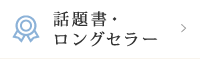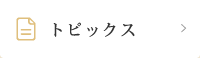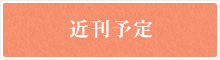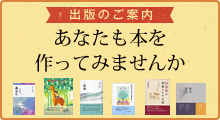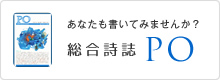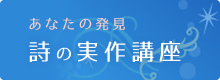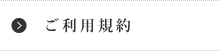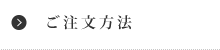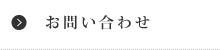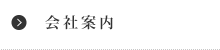![]()
197号 誘惑
197号 誘惑
- 満月祭 瀬野とし
- 白椿 戸田和樹
- 落葉 志村京子
- 西日 志村京子
- お菓子のパイが焼きあがる周りで遊ぶ子どもたちの唄 バルトーク「子どものために」を聞きながら 志村京子
- 猫の子 いっぴき 如月ふう
- 僕は歩く 阪南太郎
- 唄 加藤廣行
- ずっとかくれんぼ 斗沢テルオ
- リアル 𠮷田享子
- 帰ろう、どこかへ 下前幸一
- 周回 増田耕三
- くちなわ 川本多紀夫
- クリスタルの館 白井ひかる
- 夜明けが過ぎて 関 中子
- ~ふたりはともだち~ 中島(あたるしま)省吾
- ろれつが回らない、姦淫恐怖 中島(あたるしま)省吾
- 難病、なんてこった 中島(あたるしま)省吾
- 一人の部屋で 加納由将
- <PHOTO POEM>平和で生きましょう あたるしましょうご中島省吾
- <PHOTO POEM>巨人の目 長谷部圭子
- パレード 升田尚世
- 森のなかで 西田 純
- 河童 水崎野里子
- 死んだ兵士の残したものは 水崎野里子
- 聖少女 葉陶紅子
- 海 葉陶紅子
- お弁当箱 平野鈴子
- 春になる 平野鈴子
- 春の日に 高丸もと子
- お伽噺 尾崎まこと
- 不思議な器(うつわ) 尾崎まこと
満月祭 瀬野とし
あおく澄みわたる 五月の夜空
大きな満月が輝いて
思い出す 前に訪れた
鞍馬寺の満月祭
新緑の満月の夜は
天界から強いエネルギーが降り注ぐという
満月に供えた清水を 皆で分け頂き
すべてのものの
いのちの目覚めと平安を
祈る祭
わが家のちいさな庭
若葉が繁る背の高いモクレンのそばで
仰ぐ 満月の輝き
わたしは思わず
両掌を 器の形に差し出し
降り注ぐ月光を享ける
きょうも わたしは 視た
昼も夜も 空をドローンが飛び交い
人が燃え
若葉の木々が燃え
橋や建物が崩れていった
両掌にコントローラーを抱え
爆撃目標をピンポイントで正確に捉え
両親指で遠隔操作する
若い兵士の姿は
どこかわたしの孫に似ていて…
若葉が繁るモクレンの木のそばで
わたしは
両掌に降り注いだ月の光を
呑む
すべてのものの
いのちの目覚めと平安を
祈る
白椿 戸田和樹
仄かに紅を纏った
大柄な蕾は
花びらを開き始めると
白い衣装に衣替えする
まるで
花嫁御寮のように
少し俯き加減に
ぼくは
その景色を
何処かで見たような気がする
右手に持つ狐のお面で顔を被った花嫁は
唇に
薄く紅を差し
束ねた髪に
白い椿の花を挿していた
春の始まり
暗闇迫る黄昏時
鳥辺野に続く「ねねの道」の
リリリーン カチ
リリリーン カチ
幽かな鈴の音を
拍子木の音が刻んでいく
白椿の
垣根が続く細道に
嫁送りの行列を先導する提灯の
仄白く揺蕩う
妖の火
落葉 志村京子
黒いタートルネックのセーターを
頭まで上げて
甲羅のなかで眠る
西日 志村京子
白い壁にもたれた
影は成長していった
どこを探しても
物音は見つからなかった
お菓子のパイが焼きあがる周りで遊ぶ子どもたちの唄
バルトーク「子どものために」を聞きながら
志村京子
お姉ちゃんやお兄ちゃんの背中を追いかけ
日が暮れるまで遊んだ日々
やがて家族の庇護から離れて
美しいことや醜いことも目の当たりにすることだろう
「汝殺すなかれ」
あなたはあなたと同じ人を殺してはならない
だから
あなたはあなたを殺してはならない
あなたはあなたの内に他者(類)を内包しているから
悲しみが心を貫き 病んで
自分自身を殺めた人を非難してはならない
死者に鞭打ってはならない
*バルトーク(1881-1945)ハンガリーの作曲家。
タイトルは「子どものために」の一曲目から借用した。
猫の子 いっぴき 如月ふう
くらくらと 地獄に落ちよ
なんていふ
粋な言葉に 眩暈をおこし
地獄の蓋を覗いてみたら
炎熱地獄は 吹く風だけで
修羅の世界は 血の臭い
執念のあえぎは その胸苦しさに
何が地獄じゃ 極楽じゃ
わたしゃ 根性が すわらない
どうぞ 神様 仏様
そこそこの暮らしで よござんす
そこそこの日々で よござんす
猫の子 いっぴき 愛しとうない
ひとっこ ひとり
愛しとうない
僕は歩く 阪南太郎
僕は歩く
杖を片手に一歩一歩
誰にも見てもらえなくても
しっかり立っている桜の木々の下を
分厚い上着もマフラーも必要なくなるころ
満開の花が咲くことを信じて
雨の日も強風の日も
倒れず立っている桜の木々の下を
僕は歩く
一歩一歩
唄 加藤廣行
啄むなら 啄んでくれ
ほの暗いカーテンの内側
凍てついた時空の ひび割れた水甕の中で
俺の心が開かれる時
うぶの肢体がどんな色に染まるのか
実生の天秤にどんな光が熟するのか
見たいのは 俺も同じ
罪を分けあってこそ 星になれる俺たちだ
おまえの その嘴
それにしても何という その饒舌
夜となく昼となく
なまめかしい声音を聴いて
草原を渡ってくる欠如のそよぎにくすぐられて
分類の 熱い欲に駆られるのは
俺だけではないだろう だから
俺は話さない
ひとつぶの果実について
愛しいものの尖端について
知っている限りのことを奪わない
啄んでくれ
明けそめた領地が啄み尽くされた時
そこから どんな鳥が飛び立つというのか
青い鳥や赤い鳥 光を失った重い鳥
そんな美しいことばとは とうの昔に別れた
世界がひとつの文章だというのか
もう どうでもよいのだ
行きずりの翼たち
行きずりの青ざめた血漿
酒にふやけた まだらの頭蓋でもよい
なでまわされたものは 蒸気となれ
陽に晒され
じめついた地面を転がれ
風さえあれば
色調に弄ばれる時の石塊
水さえあれば
皿に盛られた朝のことば
ずっとかくれんぼ 斗沢テルオ
あの日のかくれんぼ
ぼくは
とっておきの場所にかくれた
もういいよ
大きな声でなんかいもさけんだ
なんかいさけんでも
おにになったけんちゃん
いつまでまっても
見つけてくれない
みんなもぼくのこと見つけにこない
秋の夕日は早くに落ちて
かくれ場所からそっとでて声あげた
ぼくここにいるよ
みんなどこにいるの
あたりはどんどん暗くなり
おうちにかえるとお勝手からゆ気
かあちゃんばんごはんのしたく
心ぽつんとぼく
かあちゃんの背中にだきついた
急にかなしくなって
涙とまらなかった
どうしたの何泣いてんの
かあちゃん――
頭ぐりぐりしてくれたけど
涙とまらない
あれから数えきれない夕暮れ
あの日泣きながら抱きついた母は
もういない
あの日からぼく――
ここにいるよって
声あげつづけているのに
誰も見つけに来てくれない
ずっと誰も
気づいてくれない
ずっとぼく――
ここにいるのに
リアル 𠮷田享子
廊下でばったり先生に出くわした
私は3枚の原稿用紙を手渡した
原稿用紙は指先から
はらはらとすべり落ちた
先生はひろいながら
「なんだ詩を書いたのか」と言われた
私は小説を書いたつもりだった
小説の勉強をしていたから…
廊下を引き返し玄関にむかった
たくさんの履物が並んでいた
そこはお寺の本堂で法要が営まれていた
喪主の席に先生が座っておられた
私は末席に座った
先生のお父様の法要だった
そこで夢は切れた
なんとも気になり先生の友人だった
K先生にお願いしてお墓参りに行った
ご健在だったお母様は
先生の三十三回忌とお父様の五十回忌を
いっしょに済ませたと言われた
びっくりして言葉もなかった
ずっと後になって気がついた
あの夢に導かれるように
私は詩の世界を歩きだしていたのだと
そしていまも詩のようなものを書いている
帰ろう、どこかへ 下前幸一
行くべき道が見えないまま
君は行かねばならない
手探りながら
しかし見境もなく
行くのだ
うつむいたまま
薄い闇の中へ
深く深く
君の後ろに足跡は消え
振り返っても
薄い闇だ
どれだけの距離を歩いただろう
誰が隣にいただろう
形のない衝動に追われて
君は行こうとする
だが
君を行かせまいとする
邪悪な手がいたるところで君を阻む
そうだ
君は仕事に行くのだった
仕事に行かなければ
朝ご飯は食べたのだったか
お母さんはどこへ行ったのだろう
喉がかゆい
でも、そうだ
行かなくてはならない
出口はどこだろう
道はどこに消えたのだろう
朝ご飯を食べなくては
ちょっとご飯を用意してください
朝ご飯を食べて
仕事に行かなくては
不安と焦燥に急かされて
君は行かねばならない
行くべき道が見えないまま
私は君の傍らにいる
戸惑いを連れて
一緒に帰ろう
どこかへ
周回 増田耕三
――何度でも回るがいい。取り返せない
心の回路を熱くするためになら
このような詩句を
かつて書いたはずだが
どの詩集を見返しても
見当たらない
もしかしたら
あったはずのその詩句は
なんらかの理由で
詩集の中から抜け出たのかもしれない
抜け出したい理由
もしくは、
抜け出さなければならない理由
など
あったのかもしれない
この度、高知県では一番の
文学賞である「椋庵(むくあん)文学賞」を受賞した
うれしいし、有難いし、
ちょっとしたパニックである
四十年以上、待ち続けた結果
七十四歳での受賞。
でも、
なんか変なのである
そこに書かれつづけたひとは
もう、どこにもいやあしないのに
まるで、周回からはずれていった
自転車のように
さびしい
くちなわ 川本多紀夫
あたりを揺るがして いきなり
藪蔭の道に
言葉も妖しく《くちなわ》が出る
黒々と とぐろを巻くと
それはさながら 神秘なウロボロス
始めなく終わりもない円環
完全と無窮永遠と不滅を体して
媾合し 妊み 殺し そして再生をする
ひと世にひと言も
ものを言うことがなく
ひと世にいちども 死んでからも
瞑ることがない《くちなわ》の双の目
この世を見透かすような
その目の奥を覗き込むと
冷ややかな彼岸が見えるかも知れない目
実は ひと言も
ものを言わなかったのではなく
遠いむかしの聖書の時代に
エバを誘惑しようとして
舌なめらかに
真理を語ったことがある
(そのためにお咎めがあって
塵を食らい 地を這うものとされた)
しばらく目をこらすうち
時を戻すようにとぐろが解かれると
完全と無窮永遠の
ウロボロスがたちまち消滅
草陰にみえていた
尻尾の残像も消え果てて
思うに《くちなわ》と
いうものは幻影なのだ
クリスタルの館 白井ひかる
電気ケトルを買った
小ぶりで軽い
スイッチを押すと
すぐにお湯が沸く
沸騰すると自動で電源が切れるから
見守る必要がない
ガスコンロにはポツンと
使い古しの笛吹ケトル
炎のあたる部分は
茶色く焼けただれている
ツルツルしていたはずの
ステンレスの光沢は
水垢のせいかザラザラしていて
見る影もない
蓋の開け閉めが固いから
水はいつも注ぎ口の方から
入れていた
洗って綺麗にしようと
蓋を開けて中を覗くと
まばゆいばかりに
光に満ちた世界が現れた
少し青みを帯びた光る鈍色の床
一点の曇りもなく
宇宙のように果てしなく広がっている
足を踏み入れて奥へと進んでいけば やがて
煌びやかなクリスタルの館に
辿り着くのだろう
こちらをじっと
見つめている者がいる
ワタシだ
私はワタシを見つめ返した
ワタシはずっとそこに
住んでいたのだ
夜明けが過ぎて 関 中子
欅(けやき)は大きく空に広がって
月の道が見えない
夜明けが過ぎて
蒲団を出られず八時過ぎ
飛び込む陽時間
寒波で今日も雪が降るでしょう
横浜の寒さは雪には遠い
遠いもの近いものが
近ごろ
はっきりする
欅の向こうは明るい
あそこでは花も開いて
蕾はぐんぐんふくらんで
欅の向こうに
欲しい時間があるようだ
雪が降らない都市のはずれ
欅が縁側に映りわたしを埋める
陽の陰に埋もれて住み続ける
日本海側はどれほど寒いか 凍みるか
~ふたりはともだち~ 中島(あたるしま)省吾
みっちゃんはアザラシというあだ名があります
みっちゃんの名前は藍沢ひめです
みっちゃんは小児病棟に入院しています
自閉症で誰も信じれません
とことことこ、と食堂から出て眠りにつきます
みぽちゃんがいました
みぽちゃんのあだ名はコナフキンです
みぽちゃんの本名は有期しおんです
みぽちゃんは全身アトピーで余命があると言われています
~ふたりはともだち~
一緒の部屋でみっちゃんのベッドで
幸せそうに一緒に寝ています
~ふたりはなかよし~
ろれつが回らない、姦淫恐怖 中島(あたるしま)省吾
不安剤デパス、台の上に置いてて
教会の一〇円給水機で水を買っている間に盗まれました
恐らく、教会長老壮年です
生涯独身者、童貞と私に代々二〇年以上言ってきたのに
教会の集合の前では
「孫が相愛大学なんとか、行きたいって言っている」と
孫の存在を
自らの口で言った
私には姦淫、他宗教禁止、婚前交渉禁止、処女しか結婚神が許してくれへん、
などいつも脅し
私にも自由があると言うと、車から「降りろー」と
二人っきりの車二人礼拝でよく脅された
私が素人童貞、生涯独身者、彼女いない歴年齢と
堂々と自負し出してきたら
向こうの言うことが変わってきた
教会長老壮年は人を脅してくる奴だが
私がストーカー呼ばわりで
頭の毛が禿げ切った
一〇年後に、壮年の牧師に替わって行けるように変わった教会
ストーカー呼ばわりの女性が他男性と結婚してから行けるようになった教会
もう、再洗礼、洗礼準備講座疲れた、生駒聖書学院で聖書は勉強しきった、
牧師免許も持っている
ストーカー呼ばわりのとこに
人生終了のポイントがあったのに
教会長老壮年も元院長も、元管理部長看護部長の壮年も
棚上げで、私が苦しんでんのなるほどと観ている
難病、なんてこった 中島(あたるしま)省吾
手の力が出にくい難病という女性のドキュメンタリー
都会人で、大学病院患者である
地方病院患者でシーティが限界の
地方病院患者ではナカッタかもしれないからか
難病が判った
私は言うのもう疲れた
結婚してて二人目が産まれるらしい
ヘルパーさんが毎日、昼、夕に食事を作りに来る
ヘルパーさんの調理で夕食、夫、娘と囲み鍋
一ヵ月に一回病院に行く
スイートマイホーム
夫は経済力がなく、夕刊配達のみの
生活保護で養ってるという
なんてこった
私も手の力が出ないときがあるが
私は工夫して過ごしている
お母さん死んだ天涯孤独でなのに
私は一週間に二回、一時間だけの掃除のヘルパー支援
女性が行ったらなんか
私がしたらあかんので
男性専用男性ヘルパーのままだ
なんてこった
私だったら個性と受け取られて、周囲に個性となる、
支援もなしは百パーセント想像がつく
一人の部屋で 加納由将
今日は 困っていた
雨は 上がりそうになく
動かないで 窓から 雨粒を 眺めていた
傘の群れは絶え間なく
音のない部屋で 活字を むさぼっていたりする
ここから 聞こえる 足音
殺風景な 部屋が 色どりを 浮かべ
会話の 片隅に ぬくもりを 感じて 体が 暖かく なっていく
これから あなたは ぼくだけに 微笑みを 向けるのだろうか
時間は 急流になって どこかに 消えてしまう
気がつけば もう 夕暮れ で 微笑みは 去っていく
部屋は 無機質になり
また 味気ない 部屋に 間取りが 現れたりする
夜は 永久(なが)く 窓には 水滴が 絶え間なく 流れている
朝は 遠く
一人の 時間が 伸びていく
今度 いつ あなたは 来てくれる?
それまで 僕は 呼吸を しているのだろうか
呼吸が 止まってるほうが 楽な気がする
それさえ できなくて 時計に 怯えている
秒針の 進む 音響が 体内に 響き
朝 まで 震えている
<PHOTO POEM>
平和で生きましょう あたるしましょうご中島省吾
平和で生きましょう
あわてないあわてない
一休み一休み
花束も御祝で
根こそぎ盗られる
感情のある顔した動物も殺処分
いつなにが死ぬか判らない
だから
死ぬのと隣合わせで
当たり前だと
平和で生きましょう
あわてないあわてない
一休み一休み
<PHOTO POEM>
巨人の目 長谷部圭子
のっぽのビルの屋上から
童話に出てくる巨人のように
眼下に広がった交差点を見渡してみる
指先で作った円の中に浮かぶ
小さなミニカーの群れ
一台 一台
ぎゅっと日常が詰まっていた
窮屈そうに身を寄せ合って
今を乗せて
未来を運んで
幸せへの轍を刻んでいる
巨人の目になって
見えてくるもの
それは やっぱり愛だった
パレード 升田尚世
鎧戸(よろいど)を開いて
太陽を放つ
青い絨毯に
トランクを置いて
硬いベッドに腰かける
十(とお)の指を
順に確かめたとき
遠く太鼓が聴こえた
もうじき
この窓の下を
パレードが過ぎるのだ
木靴に履きかえ
階段をかけ降りる
扉を軋ませて
飛び出せば
灰白色の石畳
ゆるやかな坂の街
ジャンジャンジャラーン
ズィル*1が響きわたる
――蹄を鳴らし 頭(こうべ)を垂れよ――
メフテル*2に誘われ
低く体を揺すって
~ずっと前にも
こんなだったね
ああ、驢馬とガチョウさ
道理で知っている訳か~
懐かしく
ふたり並んでついて行く
*1 ズィル:シンバルの原型で鳴り物の一種。
*2 メフテル:オスマン帝国とトルコ共和国で行われてきた伝統的な軍楽のこと。
「ジェッディン・デデン」が有名。
森のなかで 西田 純
起きている 夢
眠っている 詩
木の葉に
話しかける 言の葉
一まい また一まい
吸収されて
からっぽの 自分だけが
ただよっている
河童 水崎野里子
わたし 今日
雨ガッパを着て歩いていたら
変な子供に出会った
雨にも負けず
傘も差さないで
スタスタと歩いている
おかっぱ髪で
そう言えば 頭のてっぺんに
お皿がある
雨が溜まっていた
わかった 雨が降っても
平気なはずだ
わたしを見上げた顔は
童の顔だったけど
口が大きくくちびるではなく
鳥のクチバシみたいだった
子供にしては 大きな足で
ペタペタ大股で歩いていた
よく見ると 足の指の間に
水掻きがあった
裸だと思ったけど
よく見ると
背中に甲羅があった
河童だ! わたしは思った
あなた河童?
わたしが聞くと
ぶるるん! と
彼は答えた
わたしは河童とダンスを踊った
雨に唄えば 楽しかりけり
仲良しになった
晴れた日には
わたしも甲羅干しをする
わたしも河童になったんだもの
人間なんてもう嫌だ
殺し合いばかりしてるから
暖かいおひさまの下で
並んで甲羅干し
ここは 河童の国なんだ
カッパ アッパ 立派 葉っぱ
クッパ オッパ ラッパ ワッパ
ナッパ
サッパリわからん にんげんは
ワハハのハッハ
水掻きスイスイ
泳ぐは楽し
河童の川は 水清く
死んだ兵士の残したものは 水崎野里子
死んだ兵士の残したものは
澄んだ青空の広がる記憶
死んだ兵士の残したものは
異郷の山々 白い雪
死んだ兵士の残したものは
石ころだらけの平原歩き
死んだ兵士の残したものは
抵抗できない ドローン攻撃
死んだ兵士の残したものは
故郷に捨てた家族の幻影
清い水が欲しかった
乾いたパンが欲しかった
暖かい茶が欲しかった
眠る布団が欲しかった
死んだ兵士の眼窩には
やがてスミレが咲くだろう
異郷の土は 乾いた彼を包むだろう
故郷では 死んだ兵士に旗を振る
けれども 故郷の妻は隠れて涙
夫の私服を燃やさなきゃ
夫の写真を額に入れよう
夫と暮らした日々は飛び去る
聖少女 葉陶紅子
内側を流れる 水の音を聴く
直ぐ彳(た)つ樹皮に 裸身押しつけ
鳥の影 頭上を覆い翔けるごと
外より内へと 犯し入るもの
ぐるぐると 独楽人形になり廻る
誰の手がさす? 神との姦淫
幾つもの貌(かお)して 神は増殖し
分身を生み 誘(いざな)い煽(あお)る
処女のまま 乳房の間(あい)つたい来て
凝(こご)りなる塩 パンより貴(たか)し
降って来る名前に 膚を晒しつつ
重力を解き 産み堕とす不死
落下する影の泡立つ 徴(きざし)より
頭蓋(とうがい)の外 多世界へ跳ぶ
海 葉陶紅子
鷗(かもめ)の色は波の色 なが胸の
ごとくに海は 満ち引き満ちる
その胸に 満ち引く海の息づかい
うずめて嗅ぐは 揺籃の刻
金色と乳色に 泡立つ海と
交わり孕み 生み出だすもの
貌(かお)笑ます言葉は力 神経は
青と薔薇色(そうび)に 染めるべきもの
虹色の虹彩通し 見わたせば
小暗き海に 降るは星くず
透明ないのちとなせば 波の粒子の
透き間(あい)くぐり 五感の縁(へり)へ
秘儀使い 左右虹彩違(たが)えれば
神女ら棲まう 御代は現わる
お弁当箱 平野鈴子
小柄な彼女は長い三ツ編をしている
いつも後ろを向いて私の机でお弁当を食べる
弁当箱のフタをずらしながら食べる不思議な食べ方をしていた
おかずが見えるのが嫌なのか恥ずかしいのか
私は訊ねることをしなかった
祖母が作っているらしい
お母さんの話は聞いたことがない
お父さんはある学校の校長をしている
数学の教師と反りが合わず反抗して
チョークを投げつけられたり立たされたり
イジメに発展し学校を辞めると言いだし
私は担任の先生に相談にいった
違う数学の先生に変えてもらうことは出来ないかと話してみた
出来ないと言われた
とうとう彼女は退学の道を選んだ
担任にも寄り添ってもらえなかった
女子高の高校二年の時だった
孤独・居場所もなく・心はゆらぎ
家族の顔も見えてこなかった
どんなにか心を痛めていたのだろう
どうすることもできなかった
何も役に立てなかったことが悔やまれる
ある時彼女から連絡があり指定場所に行くと
そこは京橋のスタンドバーだった
洋酒のビンの前でシェーカーを振り
手慣れた様子でカクテルを作る彼女がいた
これが校長先生のお嬢さんの姿なのかとショックを受けた
この先彼女の人生はどうなるのか不安だった
何年かして沖縄に住んでいるとの連絡があった
沖縄海洋博の年だった
それが最後の便りになってしまった
彼女は幸せになれたのだろうか
家庭を持ったのだろうか
元気でいるのだろうか
いつまでもセーラー服姿しか浮かばず
八十歳の顔が想像できない
アンナ・カレーニナの本を読んでいたあなた
今なら振り向いてあなたがいたら弁当箱に
御馳走詰めて差しあげますのに
そう あなたは鴫野に住んでいたわね
最後に逢った日
客にチェイサーを出す細い腕が
私の脳裏に焼きついています
春になる 平野鈴子
鮪の「なかおち」を手に入れた
味に期待をこめてスプーンでガキガキとそぎとる
物価高のいまトロや中トロ並の豊かな味が安価で楽しめる
ドリップもなく舌に鮪がまとわりついてくる
山葵と醤油のエッジがきき細やかな口福をもたらしてくれる
白い皮を切り「なかおち」の骨で出汁を取る
大小の油の玉が広がる
大根・人参・里芋・コンニャク・油揚げを入れ
酒粕・味噌で味を調えみじん切りの蕗の薹を加え
春の料理に苦味を盛り熱々の粕汁を味わう
深夜一人飲む一夜酒(ひとよざけ)(酒粕の甘酒)
なんと雅味の深い呼び名であろうか
春の日に 高丸もと子
乳母車の赤ちゃんが
空に向かってバイバイしている
思わず私も空を見る
電線が見えるだけ
すれ違ったあと もう一度見上げる
やっぱり電線があるだけ
いや しかし
今度は立ち止まってゆっくり探してみる
あった!
ずっと遠くの方
うすく透けた
三日月!
ははあん
あの三日月に手をふっていたのね
あれは赤ちゃんが生まれる前に
のっていたゆりかご
それを覚えていたのね
だからあんなに うれしそうに
手をふって
三日月の向こうから
ふっとこみ上げてくる優しさのようなもの
これは何だろう
置き去りにしてきたような
哀しみのようなもの
お伽噺 尾崎まこと
君に
お伽噺をはじめよう
鬼のお面をかぶると
奥の目が泣きそうになる
お面を被せられた
彼女がそうだったように
あの子は
鬼ごっこの鬼だった
木の中を通り過ぎて
行方不明になった
誰も探さなかった みんな
日が暮れて家に帰った
あの子はきっと年をとらない
僕は そのうち大人になってしまった
人を鬼に変える情念は
怒りではなく悲哀ではなかろうか
僕は失った鬼をさらに探しつづけた
そのうちに
白髪のおじいさんになってしまった
これってお伽噺だろう?
もう鬼をさがしている時間はない
ある日 鏡をみると
一生尋ねてきた鬼がいるではないか
鬼は必ず帰ってくるのだ
摂津の茨木童子のように
君だって見えるはずだ
帰ってくるものが
これは君へのお伽噺だ
めでたし めでたし
不思議な器(うつわ) 尾崎まこと
今窓を開けると
空は大きな うつわ
とても大きな うつわ
太陽も地球も入れている
ああ、空よ
ちいさな花とアリと
あなたもわたしも住んでいる
空は うつわ
不思議な うつわ
時は うつわ
この世の始めから
この世の終わりまで収めている
とても大きな うつわ
悲しみの今 喜びの今
今 今 今
どんなに重ねても
時の うつわは溢れない
ああ 時よ
その限りない大きさは
永遠という
不思議な うつわ
心はうつわ
見えない うつわ
とても大きな うつわ
世界を入れている
空だって 山だって 海だって
入れている
見えない風だって 入れている
不思議な うつわ
あなたの うつわ
わたしの うつわ
合わせると
それは愛という うつわ
空の果てに
時の果てに
命の果てに
ああ
それは愛という うつわ